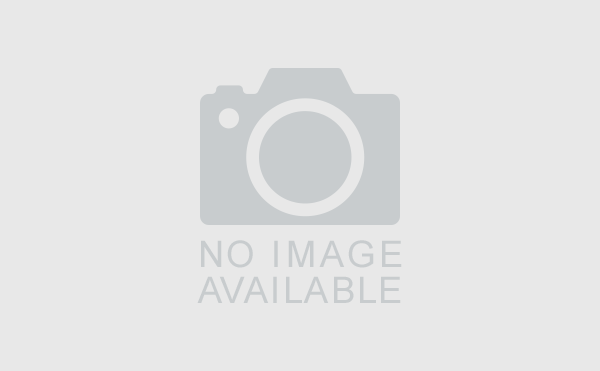ストックオプションとRSUの税金に注意!課税タイミングと計算方法を税理士が徹底解説
近年、優秀な人材の獲得や従業員のモチベーション向上のため、給与や賞与といった金銭報酬に加え、「株式報酬(インセンティブ・プラン)」を導入する企業が急増しています。
代表的なものにストックオプション(SO)がありますが、最近ではRSU(譲渡制限株式ユニット)といった新しい手法も増えてきました。
これらの株式報酬は、会社の成長と共に将来大きな利益を得られる可能性がある一方で、その税務処理は非常に複雑です。特に「いつ課税されるのか」「どの所得区分になるのか」を正しく理解していないと、想定外の納税負担や申告漏れに繋がる危険性があります。
この記事では、経営者や役員、従業員の皆様が知っておくべき「ストックオプション」と「RSU」の税務について、それぞれの仕組みと違い、具体的な課税タイミング、計算方法、確定申告の注意点を、税理士の視点から詳しく解説します。
1. ストックオプション(SO)の税務
まず、伝統的な株式報酬であるストックオプション(SO)について解説します。
ストックオプションとは
ストックオプションとは、株式会社の役員や従業員が、あらかじめ決められた価格(行使価格)で自社の株式を購入できる「権利」のことです。
株価が上昇したタイミングで権利を行使し、安い行使価格で株を取得、その後、時価で売却することで、その差額を利益として得られる仕組みです。
ストックオプションの税務を考える上で最も重要なのは、「税制適格」の要件を満たすかどうかです。
1-1. 税制適格ストックオプション
税制優遇措置を受けるための一定の要件(租税特別措置法に規定)を満たしたストックオプションです。
[特徴とメリット]
最大のメリットは、権利行使時(安い価格で株を取得した時点)には課税されず、将来株式を売却した時にのみ課税される点です。
[主な要件]
税制適格と認められるには、以下のような厳格な要件をすべて満たす必要があります。
| 項目 | 主な要件(概要) |
| 付与対象者 | 会社及びその子会社の役員・従業員、または一定の要件を満たす外部協力者(弁護士、公認会計士など国家資格保有者、エンジニアなど特定の知識・技能を持つ者) |
| 発行形態 | 無償発行であること |
| 権利行使期間 | 付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日まで |
| 年間行使限度額 | 権利行使に係る年間の合計額が1,200万円を超えないこと |
| 権利行使価格 | ストックオプションに係る契約締結時の時価以上の金額であること |
| 譲渡制限 | 新株予約権は譲渡禁止であること |
| 保管委託 | 権利行使後は、証券会社または金融機関等による保管・管理等信託が必要 |
[課税タイミングと計算方法]
- ① 権利行使時: 非課税(税金は発生しません)
- ② 株式譲渡(売却)時:譲渡所得として課税されます。
- 課税対象額: (売却価格 – 権利行使価格)× 株式数
- 税率(分離課税):合計 20.315%
- (内訳:所得税 15% + 復興特別所得税 0.315%(15%×2.1%) + 住民税 5%)
1-2. 税制非適格ストックオプション
税制適格の要件を満たさないストックオプション(例:権利行使期間が2年未満、行使価格が時価より低い、外部協力者への付与だが要件を満たさない等)は、すべて「税制非適格」となります。
[特徴]
税制適格とは異なり、2つのタイミングで課税が発生します。
[課税タイミングと計算方法]
- ① 権利行使時:給与所得(または雑所得・退職所得)として課税
- 課税対象額: (権利行使時の時価 – 権利行使価格)× 株式数
- 所得区分と税率:
- 給与所得(役員・従業員の場合):他の給与と合算され、総合課税(累進課税:所得税5%~45% + 住民税10% + 復興特別所得税)が適用されます。
- 雑所得(外部協力者の場合)や退職所得(役員退職時に行使した場合など)となるケースもあります。
- 注意点: 株式をまだ売却しておらず現金化していないにもかかわらず、高額の税金が課される可能性があります。納税資金の準備が不可欠です。
- ② 株式譲渡(売却)時:譲渡所得として課税
- 課税対象額: (売却価格 – 権利行使時の時価)× 株式数
- *取得価額は「権利行使時の時価」となります。
- 税率(分離課税):合計 20.315%
- (内訳:所得税 15% + 復興特別所得税 0.315% + 住民税 5%)
- 課税対象額: (売却価格 – 権利行使時の時価)× 株式数
2. RSU(譲渡制限株式ユニット)の税務
次に、近年導入が急増しているRSU(Restricted Stock Unit:譲渡制限株式ユニット)について解説します。
RSU(譲渡制限株式ユニット)とは
RSUとは、会社が定めた期間(例:3年後など)継続勤務するなどの条件を満たした場合に、会社の株式を無償で受け取れる「権利」(またはその時点の株価に相当する金銭)を指します。
[ストックオプション(SO)との大きな違い]
- 行使価格がない: SOは「あらかじめ決めた価格で買う権利」ですが、RSUは条件達成時に「無償(タダ)で貰える」のが一般的です。
- 株価下落時のリスク: SOは株価が行使価格を下回ると価値がなくなりますが、RSUは株価が下がっても、無償で貰える限りは価値がゼロになりにくいという特徴があります。
[課税タイミングと計算方法]
RSUも税制非適格SOと同様、2つのタイミングで課税されます。
- ① 権利確定・株式交付時:給与所得として課税
- 課税対象額: (権利が確定し、株式が交付された時点の時価)× 株式数
- 所得区分と税率:
- 給与所得(役員・従業員の場合):他の給与と合算され、総合課税(累進課税:所得税5%~45% + 住民税10% + 復興特別所得税)が適用されます。
- 注意点: 株式交付の時点で給与所得として課税されます。会社側で源泉徴収されるのが一般的ですが、税額の計算根拠は必ず確認が必要です。
- ② 株式譲渡(売却)時:譲渡所得として課税
- 課税対象額: (売却価格 – 株式交付時の時価)× 株式数
- *取得価額は「株式交付時の時価」となります。
- 税率(分離課税):合計 20.315%
- (内訳:所得税 15% + 復興特別所得税 0.315% + 住民税 5%)
- 課税対象額: (売却価格 – 株式交付時の時価)× 株式数
3. 株式報酬と確定申告の重要ポイント
ストックオプションやRSUで利益を得た場合、原則として確定申告が必要です。特に以下のケースでは注意が必要です。
確定申告が必須となる主なケース
- 税制適格SOの株式を売却して利益(譲渡所得)が出た場合。
- 税制非適格SOやRSUの株式を売却して利益(譲渡所得)が出た場合。
- (※特定口座(源泉徴収あり)で取引し、そこで納税が完結している場合を除く)
- 税制非適格SO(権利行使時)やRSU(株式交付時)で給与所得が発生した場合。
- 「会社が源泉徴収してくれているから申告不要」と誤解されがちですが、以下のいずれかに該当する場合は、源泉徴収済みであっても確定申告が必要です。
- 年収が2,000万円を超える場合
- 株式報酬による給与所得(または副業など)が年間20万円を超える場合
- 複数の会社から給与を受けている場合
- 「会社が源泉徴収してくれているから申告不要」と誤解されがちですが、以下のいずれかに該当する場合は、源泉徴収済みであっても確定申告が必要です。
申告漏れのリスク
もし確定申告を怠ったり、所得区分を間違えたりすると、税務調査で指摘を受け、本来納めるべき税金に加えて、延滞税や過少申告加算税(場合によっては重加算税)といったペナルティが課されることになります。
特に、非適格SOやRSUの権利行使・交付時には、累進課税が適用されるため、他の所得と合算すると税率が跳ね上がり、想定以上の納税額になることも少なくありません。
外国親会社の株式報酬(外貨建て)の注意点
外国親会社(例:米国本社など)からストックオプションやRSUを付与されている場合、権利行使や売却の計算はすべて外貨建てで行われます。
日本で確定申告する際は、これらを適切な為替レートで円換算する必要があり、計算が非常に煩雑になります。為替レートの適用日(行使日、売却日など)を間違えると税額も変わってきてしまうため、細心の注意が必要です。
まとめ:株式報酬の税務は専門家にご相談ください
ストックオプションやRSUは、従業員にとって大きな夢のある制度ですが、その税務は非常に複雑です。
- 「自分は税制適格か非適格か?」
- 「RSUの給与所得はいつの時点でいくら発生したのか?」
- 「外国株の円換算レートはいつの時点か?」
これらの判断をご自身で行うのは困難な場合も多く、誤った申告は大きなリスクを伴います。
当事務所では、ストックオプションやRSUに関する複雑な税務計算や確定申告の代行、節税に関するアドバイスを専門的に行っております。ご自身の状況に応じて、適切な納税が行えるよう万全のサポートをさせていただきますので、ご不安な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
弊事務所は、経営に関わる税務・会計の課題解決に特化しています。当事務所の報酬体系や具体的なお見積もりにつきましては、まず貴社の現状をお伝えいただき、個別にご依頼ください。お客様の事業が安心して成長できるよう、専門家として確実なサポートをお約束いたします。